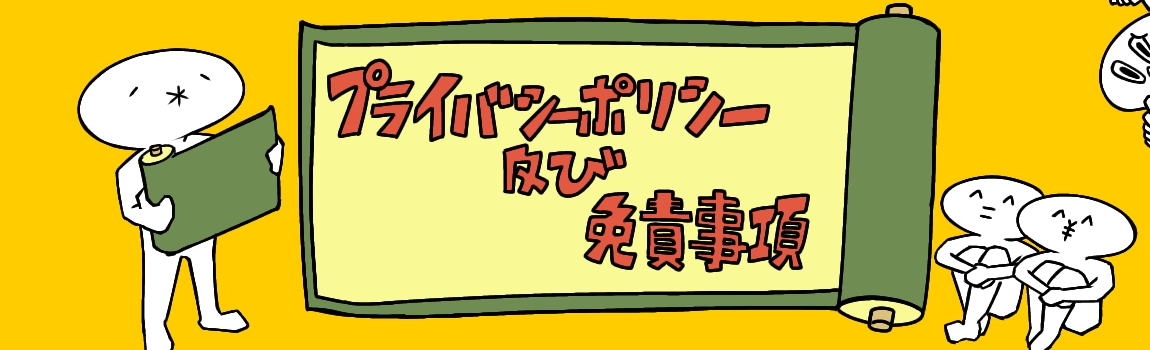【まとめ】AIタッグノベル!!『下衆と皮肉劇場〜みんな田中〜』
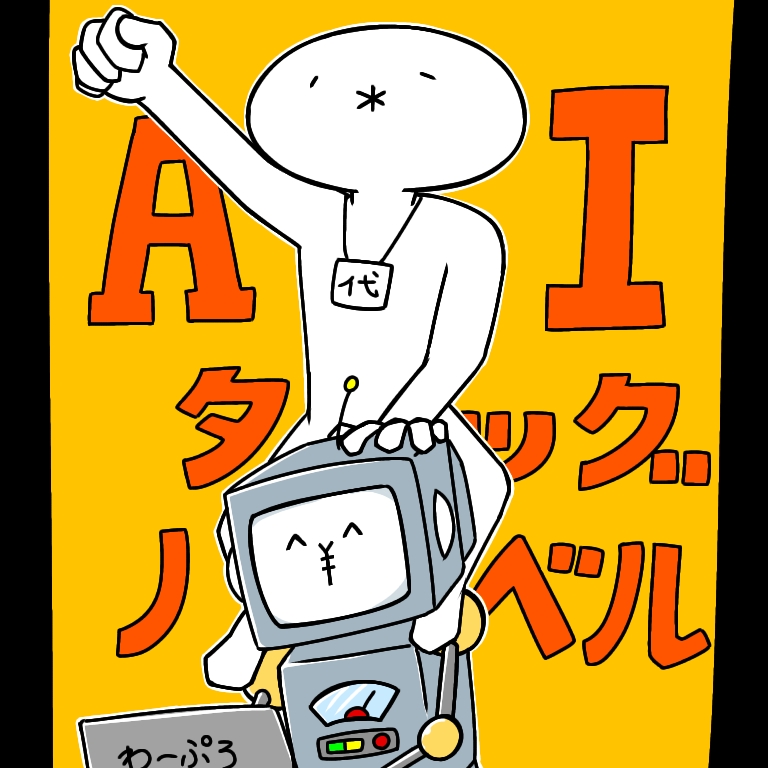
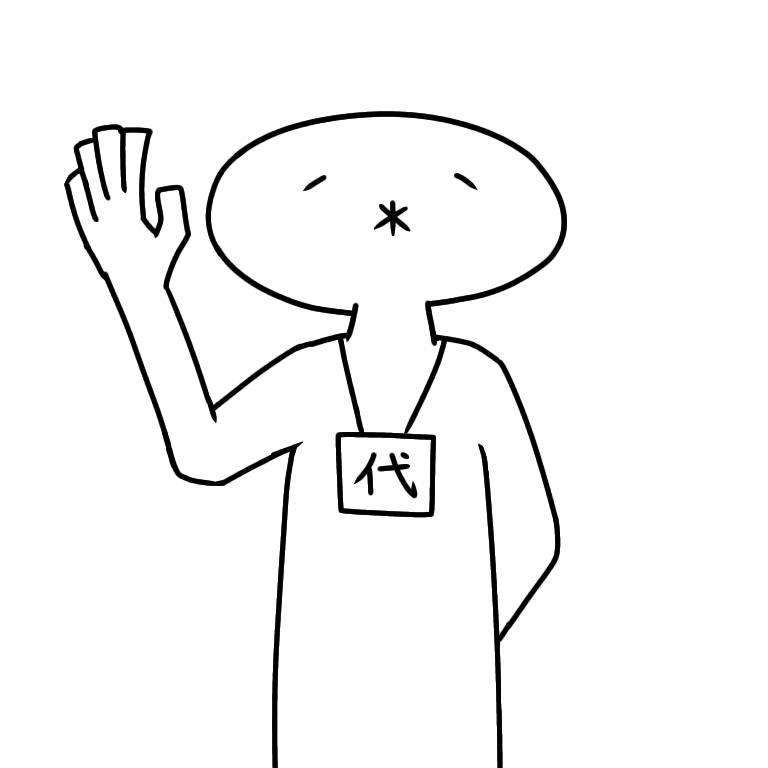
おはよう、皆の衆。定次さんです。
今回は先日まで更新していたAIタッグノベルのまとめとなります。
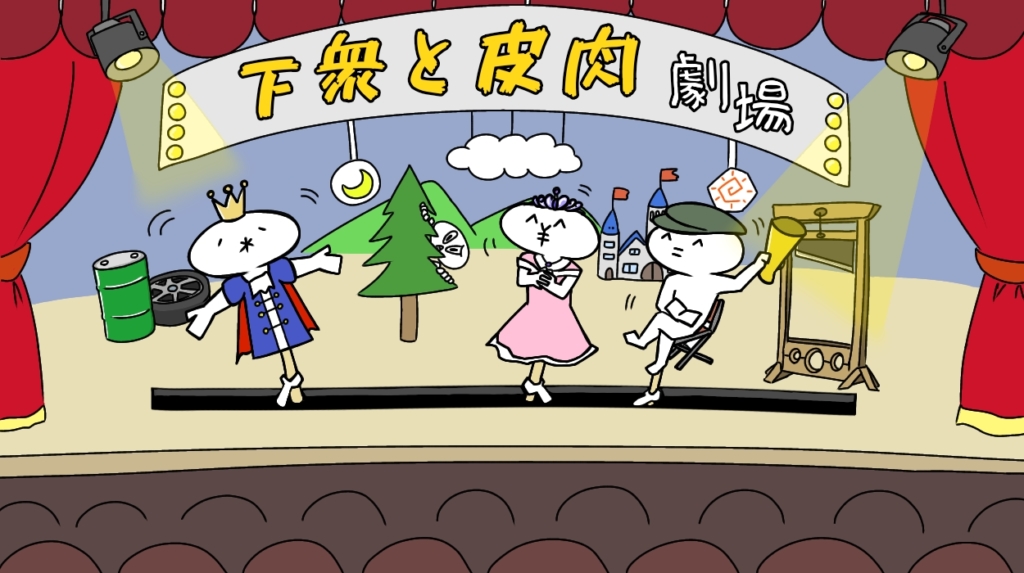
男は項垂れていた。ぱんぱんに膨れ上がった麦穂のように傅き、口からは汚らしく涎を垂らしている。汚い雫が地面を濡らし、小さな溜ができている。
ガード上を走る列車の車窓から漏れる明かりが涎溜を朧気に照らした時、一人の人間が声をかけてきた。
「あのォ……もしもし?起きてます……?」
男は反応を示さない。生きているか死んでいるかもわからない姿勢のまま、夜風に揺られて力なく体を揺らしている。
「うーん、参ったなぁ……。もしかして死んでないよね?」
少女の口調には若干の焦りが含まれていた。彼女はポケットからハンカチを取り出し、男の顔に被せるようにして当てた。すると男の体がびくんと震えた。どうやら意識を取り戻したらしい。
「あ……あ……」
男は何か言おうとしたようだったが、どうやらとても腹を空かせているらしく、言葉よりも先に腹の音が大きく返事をした。
「ぐう」とも聞き取れるのか怪しい咆哮に少女は安堵し、思わず握っていたハンカチを放り出した。
放り出したハンカチはクシャクシャに丸まり、汚らしく照らされた涎に覆い被さった。
「アハハッ!!」
けたたましく鳴り響いたガード上の轟音を追いかけるように漏れた笑い声がピンと張り詰めた緊張感を緩める。
男もその姿に遂には顔を上げ、目を丸くして少女を見つめていた。
「君!名前は!?どこから来たんだい?」
「えっと、私は…………その、通りすがりです!」
そう言って少女は胸を張ってみせた。
男がその言葉を信じるかどうかは別として、少なくとも彼女の姿はとても"通りすがり"には見えなかった。
「ところで・・・」
何かを言いかけようと口を開いた男だったが、ハッと何かに気がついたように慌てて立ち上がった。
丸く見開いていた目をより一層大きく広げ、慌ただしく両手で自らを弄り始めた。
「ない!ここにあった・・・俺の大事な・・・」
ひとしきり周りを見渡した後、目の前で棒立ちしている少女に視線が向けられた。
つい先程まで親しみを見せていた表情は一気に険しさを帯び、慌ただしく振り回されていた両手は勢い良く少女の肩を掴んだ。
「おいお前!!この辺に財布を落としたはずだ!!知らないか!?」
「ひゃっ!?し、知りませんけど……」
突然の出来事に少女は驚き、反射的に首を横に振った。
それを見た男は少女の両肩を掴む手に更に力を込め、
ようこそ!ここは場末のバーだがそれなりにお酒は揃ってるぜ!
つまみはちくわぶにピーナッツを詰めて炙ったものしかないがそれでも良いって言うなら存分に寛いでいってくれ!
勿論タダとは言わないぜ!犬小屋が1棟容易に買えるくらいの金額は用意しておけよ!
じゃあな、俺は家に帰るぜ!
そんな事を言うつもりであったのだが、男の喉から声が出ることはなかった。
その代わりに出たものは乾いた空気の音と大量の血反吐だった。
男の胸には大きな穴がぽっかりと開いていた。
さっきまでの威勢は一体どこから湧いて出てきていたのか、今一度男は崩れるように座り込んだ。
てらてらと溜まった涎にじわじわと血が混じる。
先程まで目の前に立っていた少女は本当にいたのだろうか?今この世界は現実の世界なのだろうか?薄れゆく意識の中で答えの見えない疑問だけが頭の中を交錯する。
ジャリッ……ジャリッ……
遠ざかっているのか近づいているのか、足音が聞こえてくる――。
それは死神が鳴らす靴音なのか。男は最後の力を振り絞り、目線だけを上に上げた。
「ごめんね」
そこには月光を浴びながらこちらを見下ろす少女の姿があった。
「私も本当はこんなことしたくはないんだけど、仕方がないよね?」
そう言うと少女はゆっくりと後ろ手に構えていたナイフを大きく振りかぶった。
背後を照らす月光が鋭利な刃先をぎらりと照らしているが、その眩しさとは裏腹に逆光に照らされた少女の影は塗り潰されたかのように漆黒に染まっていた。
彼女はどんな表情をしているのだろう。笑っているのか、怒っているのか、はたまた悲しんでいるのか――その表情は今にも刃物が突き立てられようとしている距離であってもまるで見て取ることができない。
男はもう抵抗しようとはしなかった。
最早これまでだ。全てを諦めたように男は目を閉じた。
―――しかし、いつまで経ってもその痛みが襲ってくることはない。
代わりに訪れたのは全身を包み込むような温かさと心地よい揺れだった。
目を開けるとそこは見知らぬ土地だった。具体的に言えば見たこともない駅だった。
先程まで見ていた光景は夢だったのか定かではないが、男は涎を垂らしながら電車の長椅子でうつらうつらと船を漕いでいたことに気が付いたのだった。
「……ここはどこだ?さっきの少女は?」
プシューという小気味よい音と同時に扉が閉まり、間もなく電車がゆっくりと動き始める。
ホームの明かりが遠ざかり、次第に窓の外が暗くなっていく。
「……今何時だ?」
周りを見渡すもそれといった情報が見当たらない。乗客もまばらで、ただ男にとってわかることは暖房がとても心地の良いものであったという感覚だけだった。
「……」
暫くぼんやりとした頭で考え事をしていた男だったが、やがて思考することを止めた。
今は取り敢えず状況を整理することが最優先であると考えたからだ。
「……よし」
まず最初に思い出したのは自分が何故このような場所にいるかということである。
男の名前は『田中』。
「そうだ、俺は田中だ」
思い出したかのようについ自分の名前を口にしていた。
電車は本格的に速度を上げ始め、揺れが激しくなる。
足元が覚束ない中、気にも留めない田中はすっくと立ち上がり、唐突に周りを見渡し始めた。そして近くに座っている他の乗客に目をつけるやいなや、吊り革に掴まりながら猿のように車両を移動し始め、飛びかかる勢いで問いただした。
青年は目を丸くして田中を見ていたが、少し間をおいてから怪訝そうな表情へと変え、耳にかけていたイヤホンを外しながらこう言った。
「……どちら様ですか?」
「えっ?」
思わず素の声が出てしまう。
青年は眉間にシワを寄せて、もう一度同じ言葉を繰り返した。
「いや、だからあなたは誰なんですか?」
「い、いや、俺だよ!田中!」
しかめた表情を更にくしゃくしゃに歪め、青年は取り外したイヤホンを耳に戻して素早く席を立った。
揺れる車両にふらつかせながら連結部分の扉にまで着いた時、今一度田中に一瞥を投げ、彼は隣の車両へと姿を消していった。
「……何なんだよ……」
吊り革に両手をかけて磔にされたようにうなだれる田中は真っ暗になった車窓に反射する自分の姿を見てため息をついた。
そこには疲れ切ったサラリーマンの顔があった。
―――
――――――
――――――――――
「……ここはどこなんだ」
再び意識が覚醒した時には田中は再び電車の中にいた。
車内には相変わらず人は少なく、アナウンスもない。
窓から見える景色も見覚えのあるものではなかった。
よく来たな!ここはあいも変わらず場末のバーで終焉の地だ!
今日のちくわぶは地獄の業火に焼かれてよく焦げているが、俺の中ではわりと自信作だと思ってるぜ!
あとは勝手にやってくれ。遠い空が恋しいから外の世界を簡単に歩いてみたいんだ。
今や車輪となったこの足は全人類の希望であり、夢であり、そして物語の終わりなのだ。
――――
「……これは?」
不意にポケットの中で何かが振動している。
取り出してみるとそれは携帯電話だった。
「こんなもの持ってたか?」
首を傾げるが、どうも記憶が曖昧ではっきりとしない。
取り敢えず電話に出てみることにする。
「もしもし」
もしもしというのは元々「申す申す」という一言を語源としているようですが、更に遡れば「おいおい」というのがルーツだそうです。
もし道端で「おいおい」なんて声をかけられたらそれは過去からやってきた人であり、現代という時代の激流に抗う人の象徴となるので大事にしてあげましょう。
現代に住まう「妖怪おいおい」。彼らは人の闇に巣食う恐ろしい存在なのではなく、古き良きを追い求めるシーラカンスみたいなもんです。大事にしてあげましょう。
ではまた次の機会に。
「はい、田中さんですね。お待ちしておりました」
「……あぁ、どうも」
聞き慣れた女性の声で我に返った田中は辺りを見渡したが、相変わらず乗客の姿はない。
妖怪おいおいは嘆いた。その声は野を越え山を越え、愛する者の住む隣の村にまで強く、そして物悲しく響いたのだ。
彼の足元に力なく横たわる女性の横にはそれにまた縋る子供が一人、二人……おいおいが涙をこぼす度にその数は増えていき、次第に周囲を覆い尽くした。
風に揺れ、ざわざわと騒ぎ立てる木々達も寝静まる満月の夜、月明かりに照らされた彼らの顔はすでに妖怪おいおいと化しており、雲に隠れ闇が広がった瞬間に彼らは音もなくその場から姿を消した。
こうして妖怪おいおいは人々の前から忽然と姿を消してしまった。
――
「もしもし?聞こえますか?」
「えっ?あっ、はい。すみません」
耳元にあてていた携帯電話を離して画面を見ると『鈴木』と表示されている。
(鈴木……?)
またしても身に覚えのない記憶が必死に田中の中枢をこじ開けようとする。
田中にとっては確かに聞き覚えのある声である。しかしこの状況からかどうも飲み込むことができず、遂には頭を抱えてしまった。
汗臭く湿った頭を掻き毟るとハラハラと細かく毛が抜け落ちた。それと同時に嗚咽が止まらなくなり、電話の向こうからは焦った声が聞こえてくる。
「もしもし?大丈夫ですか!?」
「はい、えぇ、はい。問題ありません。ちょっと頭痛がして……」
「わかりました!すぐにそちらに向かいます!」
プツッと切れる音がした後、田中は携帯電話を床に投げ捨てた。
床に転がる携帯電話を見て田中はハッと我に返った。
現状を知る唯一のヒントであるかも知れないというのに、今しがた捨ててしまったそれの画面はバキバキとヒビを入れて天を仰いでいる。
田中だけを乗せて走る車輌は尚も加速を続け、比例して車体が大きく揺れる。
「走行中は揺れますのでお立ちの方は十分にお気をつけください」
無機質なアナウンスが車内に流れるが、田中の耳にはまるで入っていない。前かがみになって車内の揺れとともにくるくると回る携帯へと手を伸ばそうとする。
――その直後、車体が大きく揺れて田中の体は大きく前に倒れてしまった。同時に指先が弾いた携帯が長椅子の奥へと勢い良く飛んでいった。
「あー……」
大きくため息をつく田中の背後からコツンという小さな衝撃があった。
振り返ってみるとそこには一人の女性がいた。先ほどまで誰もいなかったはずなのにいつの間にそこに現れたのか、彼女は不思議そうな表情でこちらを見上げている。
「え……」
思わず声が漏れる。先程まで車内には田中以外には誰もおらず、気配なんて何一つしていなかった。
田中は生まれたての子鹿のような情けない四つん這いの姿勢で尚も硬直している。器用にも車輌の揺れに対しては踏ん張りがきくようだ。
「えっとですね……あー……携帯?先程お話しましたよね?」
「鈴木……さん?」
「はい、そうです」
尚も困惑している子鹿の反応に彼女は少し戸惑ったようにはにかんで返事をした。
「私ね、電車の妖精なの。困ってる人を見かけたら声をかけて惑わして……ふふふっ」
悪戯っぽく笑う彼女の言葉を聞いて田中は更に混乱する。
「いや、でもさっき電話に出た時は鈴木さんの声じゃなかったような気がしますけど」
「あれ?おかしいなぁ。ちゃんと鈴木さんの声で喋れたんだけどな」
そもそも鈴木が誰なのかもわかっていないが、明らかに目の前に立つ少女は異質な存在だった。
「冷やかしならやめてくれ。今俺はそれどころじゃないんだ」
視線を戻して再び携帯電話の後を追う。
わたわたと四肢をばたつかせながら逃げる様は相変わらず子鹿のようだ。
「そんなこと言っていいのかな?この電車から降りられなくなっちゃうよ?」
子鹿の前に少女の華奢な足が立ちはだかった。
どうやら逃げ道を塞がれてしまったらしい。
田中は諦めたようにその場に座り込み、膝を抱えて丸くなった。
「どういう意味なんだ?」
「そのままの意味だよ。この列車はもうすぐ終点につくから、そこで降りたら二度と戻って来られないんだよ」
そんなことはどうだっていい。
今日は頭が痛いから今日はここで終わり。終了です。
「俺はまだ終われない。まだまだやることが残ってる」
「それは残念。でも仕方がないよね。あなたはここで降りる運命だから」
「何を言って……」
――その時、車輌がガタンと大きな音を立てて止まった。
「さぁ着いたよ。ここが終点だよ。」
――少女の声が背後から徐々にフェードアウトしていく。田中は虚ろな表情で周りを見渡す。つい先程まで見ていた光景はそこに広がっておらず、気が付くと窓の外は自宅最寄りの駅だった。
まばらどころか誰もいなかった車内にもそれなりに乗客が見て取れ、皆同じように疲れ切った顔をしている。
ピリリリリリリリ……!!
ホーム全体に響き渡る笛の音を聞いて田中は慌てて電車を降りた。
(夢か?)
改札を出て空を見上げると雲間から覗く月が綺麗に輝いていた。
(夢にしてはあまりにも鮮明すぎる)
田中はしばらくその場で呆然と立ち尽くしていたが、やがてゆっくりと帰路についた。
歩き慣れた道を進んでいくとやがて大きなガードの下へと辿り着いた。この近辺は電灯が少ないためにいつも薄暗く、それでいて治安があまりよろしくない。
時折ガードの上を走る電車の音に誰しもがおっかなびっくり歩くものだが、田中の耳には当たり前のことなのか、それとも先程までの幻想に混乱しているのか、轟音も耳に入ってこない。ふわふわとした足取りで一歩一歩自宅の方向へと足を進めていく。
暫く歩くと目の前に一人の人間が壁際に背中を寄せて座り込んでいるのが見えた。
街灯の光が届かない場所にいるためにはっきりとは見えないが、体格的に男性だろうか。
田中は少しだけ警戒しつつ、その人物へと歩み寄る。
「あのー……大丈夫ですか?」
「……」
反応はない。
田中は伸ばそうとした手を思わず引っ込めた。
こんなにも近くに人が立っているというのに、男は尚も反応を示さない。生きているか死んでいるかもわからない姿勢のまま、夜風に吹かれて力なく体を揺らしている。
(俺だ……)
「俺だと思ったか?残念だったな。俺なんだよ」
後ろから聞こえてきた謎の声に田中は振り返ったが田中は田中ではなかった。田中は田中であって田中であるもの。後ろから聞こえてきた田中は必ずしも偽物という可能性をはらんでいるわけではなく、本物の可能性が実に高い。
「伸びてきた手に肩を掴まれた」
そう供述する田中は壁にもたれる田中であり、掴んだ田中は、
「伸ばした手は引っ込めた」
とのたまっている。
それを傍観していた田中に至っては、
「俺は田中じゃない。だが、彼らもそうではないようにも思える」
と甲高い声を上げてガードの上を思い切り駆け抜けていった。
「どうなってるんだ……?」
田中は一人呟いた。
「なぁ、お前は誰だ?」
「お前こそ誰なんだ?」
田中は問い返した。
「俺は田中だ」
「違う。俺は田中じゃない」
「俺は鈴木だ」
「いや、俺が鈴木だ」
「俺は田中じゃない」
「俺は鈴木じゃない」
「俺は田中じゃない」
「俺は鈴木じゃない」
「俺は田中じゃない」
「俺は鈴木じゃない」
「俺は田中じゃない」
「お前は鈴木じゃない」
「俺は鈴木じゃない」
「お前は田中でもない」
「俺は田中だ」
「俺は田中じゃない」
「お前は田中だ」
「俺は鈴木だ」
「鈴木は田中だ」
「田中は田中だ」
「違う、俺だ」
「どうも、佐藤です」
「どうも、高橋です」
「どうも、田中です」
「どうも、鈴木です」
「どうも、山田です」
「どうも、田中太郎です」
「どうも、鈴木三郎です」
いつの間にか田中は田中ではなくなっていた。周りを複数の人間が取り囲み、有象無象と化していた。
知らない顔が押し寄せてくる。一同が流れるように田中に無機質な笑顔を向けてはどこかへと消えていく。
「これが人の優しさ……?」
田中の目からは涙がこぼれていた。人の波に逆らうようにその場にへたり込み、項垂れるように崩れていった。
足元には汚らしく小さな溜が広がっている。
やがて訪れる静寂の中、田中は思い返す。
――今日は朝から頭痛が酷かったことを。
(あぁ、そういうことか)
田中は静かに目を閉じた。
「ねぇ、君、大丈夫かい?」
ぼやけた視界の先にはごつめの革靴が街灯に照らされていた。
涎と涙が入り混じった汚い溜の上に置かれた足を追って顔を上げていく。重たい頭を持ち上げて徐々に視線が声の元へと近づいていく。徐々に姿が見えてくる。徐々に頭痛が増していく。
「ん?何で泣いているんだい?ほら、立てるかな……?」
その男は中年くらいの年齢だろうか。背丈はそれほど高くはなく、髪はやや薄く、肌の色が黒い。
無意識に掴んだ男の手は温かかった。そしてゴツゴツと固く、力強さがあった。
ぐいと引っ張られた田中はあたかも空を飛んだかのように体を大きく浮き上がらせ、そしてそのままきれいに着地をした。
空を飛んでいる最中、田中の目には世界がとてもゆっくりに見え、そして大きく見えた。
しっかりと両足を地面に着かせて直立する田中。伸ばした右手は未だに持ち上げられており、その先には逆光で陰った男の顔がにやりとほくそ笑んでいた。
「ありがとうございます……」
お礼を言う田中だったが、その言葉は震えており、声は今にも泣き出しそうなほど弱々しかった。
男はそんな田中の肩を軽く叩いて、「気にしないでいいよ。ところで、君は一体誰だい?」と言った。
「どうも、佐藤です」
田中は答えた。
「俺も鈴木です」
「俺も高橋です」
「俺も田中です」
「俺も鈴木じゃなくて田中なんです」
「えっ?……そうか。なら仕方ないね」
『もうみんな田中でいい』
そんな空気になっていた。
「自分自身が誰だかわからなくなっていた」
雰囲気に流され、今や田中ではなくなってしまったかつての田中にはすでに田中の面影はなく、また新たな人生を歩み始めようと元田中の自分探しが始まった。
社会は田中を求めているが、その圧倒的多数派の意見から逃れようと孤独に生きようとする人間もいる……。
彼らが本当の自分を見つける時は一体どれだけ先の未来になるのだろうか。(完)
【登場人物】(年齢は初登場時のもの)
・高橋
・田中太郎
・佐藤
・鈴木
・山田
・田中次郎
・「ねぇ、知ってる?」
・「何を?」
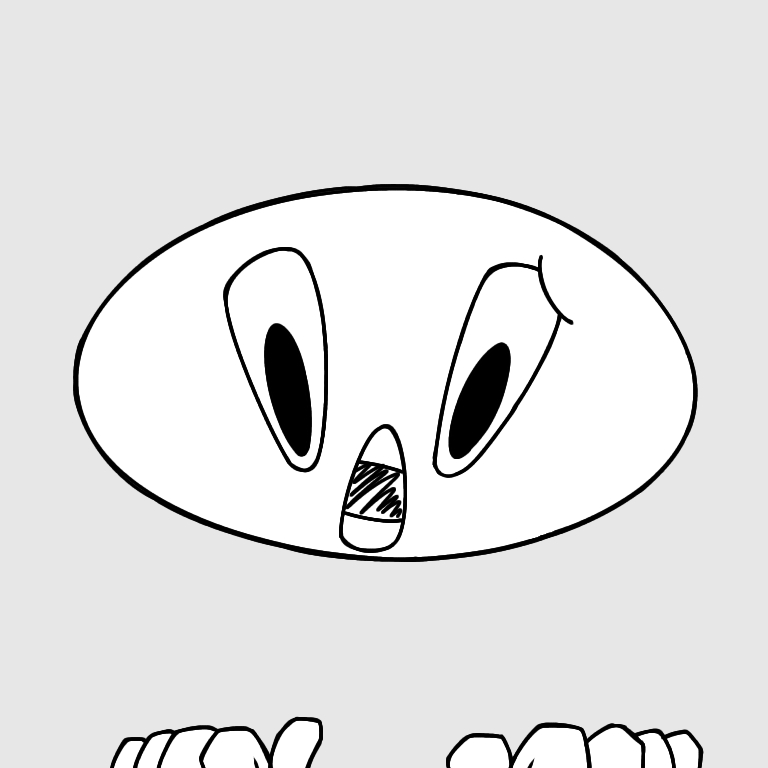
総合評価:★★☆☆☆









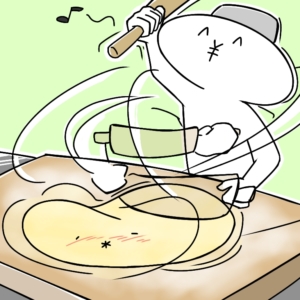



 【定次さん】
【定次さん】