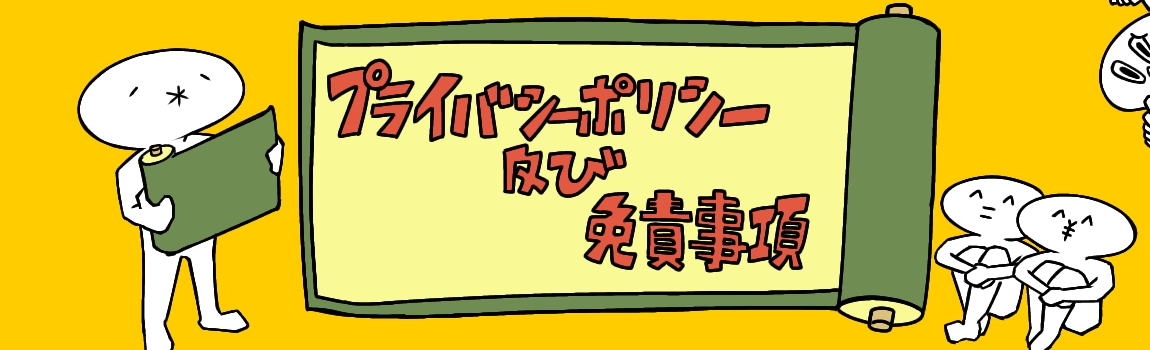モーソーロンパ!:隣に美人のお姉さんが引っ越してきた!


おはよう、皆の衆。定次さんです。
隣人にジジババが越してきたところで何のときめきも覚えませんが、もし万が一美人の異性が引っ越してきたということがあったなら、それはもうロマンスの始まりなのかもしれません。
ドラマや小説の設定としてよくある『隣人との人間関係』。
その人間関係が築き上げる形は運命的なものから始まり、単純に色恋だけではなく、かけがえのない友情などと幅は広いです。
たかだか近所に引っ越してきて、たまたまばったりと鉢合わせて、偶然ときめいてしまった――導入部分は基本的にそれだけだというのに、いつの時代も人々はそんなロマンに心躍らせています。
しかし現実の出会いとはそんなロマンとは真逆を行き、理想こそ抱くものの、どうしても人との間に壁を作ってしまいがち。
自分ファーストな昨今の人々からは運命的な出会いの欠片をまるで感じられません。
一戸建てよりも集合住宅の需要のほうが圧倒的に多く、ご近所付き合いの機会も多くあるというのに、実際問題玄関の扉の向こうの世界は、簡単な挨拶だけ交わして後にするような希薄な人間関係が広がるばかりです。
他人との接触をリスクヘッジとして捉えるこのご時世だからこそ、一層そんな出会いを絵空事と捉える人が増えました。
自分ファーストな時代にはマッチングアプリでの出会いが一番お似合い。出会い頭の運命なんて夢のまた夢……挙句の果てには『隣人ガチャ』と揶揄されるのがオチです。
「夕飯を作りすぎてしまったからお裾分けに来ました」
そんなセリフは昭和の時代から耳にしたことがない人も多いでしょう。
牛の糞尿の臭いが充満する辺鄙な田舎であれば、今もジジババどものコミュニケーションツールの一つとして自宅の畑で仕上がった歪な野菜のお裾分けがあるものですが、『料理を多く作りすぎてしまったので……』といったロマンある話自体、現実で見ることは疎か、昨今放映されるドラマの脚本でもなかなか見受けられません。
『現実でありえないことはドラマでもそうそうあり得ることではないだろう』とリアリストぶった考えを振りかざし、何の面白みもないフラットな日常を過ごそうとする人にこそ、意外にもそんな思わぬ出会いが訪れることがあったりするものです。
――遡ること今年の3月。
年度末ということもあってか、私の住むアパートからもちらほらと卒業するかのように退去する住人が見受けられました。
気が付けば我が家の隣の部屋が空き、下の部屋も空室に。
隣室からの暖房がないことで若干の肌寒さを覚えつつも、多少騒いだところで迷惑にならないことに私は一時の自由を満喫しながら生活をしていたのですが――、ある日気がつくと隣室のインターホンの電源が点いており、駐車場にも一台の見知らぬ車が駐車していました。
部屋が空いてからおおよそ2ヶ月半。長いようで短いようで、アパートに空いた穴の一つがようやく埋まったと理解して私は少しばかり心の奥底で歓喜しました。
自由に騒げたのも悪くはなかったですが、何となく隣室に誰もいないという事実の方が物悲しい。
だからこそ私はその瞬間にちょっとばかりはしゃいでしまい、ベランダから身を乗り出して新たな車の持ち主を見てみようとしたのでした。
ちょうど車から降りてきたのは一人の女性。それも何だか綺麗で若そうな見た目をしています。
前まではむさ苦しい男が住人だったので、今回こうして綺麗な女性が入ってくるのは、一人の男として胸が踊ってしまいます。
間もなくして私の視線に気がついたのか、女性と目が合ってしまいました。
あまりに身を乗り出していたたその姿はあまりに不自然。それでいてなかなかどうして引っ込みようがなかったので私は誤魔化すように視線を泳がせながら徐々に部屋の中へと姿勢を戻していったのでした。
部屋の中に体が引っ込む際に見えた女性の表情。
最初は私の姿をみて随分と驚いたように大きな目を見開いていましたが、やがて頬を赤らめるかのように照れた表情でスッと目を背けたように見えました。
――変な人に思われたかな?と頭をポリポリとかきながら若干の後悔こそしたものの、結局は顔を合わせた際に挨拶する程度の関係でしかないでしょうから、何ら気にも留めませんでした。
後日、朝方に引越し業者がやってきて、ドタドタと騒々しく引っ越し作業が進みます。
私が仕事から帰ってくる頃にはすっかり作業も終わったようで、何もなかった窓には既に白色を基調としたカーテンが張られていたました。
このご時世、引っ越しの挨拶にくることはないだろう――そんなことを考えつつも、先日の反応がちょっとばかり片隅に残っており、もしかしたら……とあらぬ期待を膨らませます。
『ピンポーン』
妄想捗る夕方と夜の境目の時間帯。虚を突くかのようなタイミングで心当たりのないインターホンが鳴りました。
特別何か配達を頼んでいるわけでもないし、宗教の勧誘を許しているわけでもない……で、あればやはりこのインターホンの先には……。
モニターに映っていたのは先日ベランダから見かけた隣室の女性。
手には何か大きな物を持って少し気恥ずかしそうにモニターから目を背けて待っていました。
「どちら様ですか?」
白々しい態度でマイクに話しかけると、女性はニッコリと笑みを浮かべて隣室に越してきた者だと簡単に挨拶をしてくれました。
私からすればその事実は既にもうわかりきったこと。問題は何の目的でその得体のしれない大きな物を持ってきているかです。
どことなく何かを察したような雰囲気を出して玄関を開ける私。
向こうもそんな雰囲気に助けられたのか、咄嗟に抱えていたものを私に向けて「肉じゃがを作りすぎてしまったので!」と一歩踏み込んできました。
簡単なお菓子やタオルといった粗品であればわかりますが、何故に肉じゃが?
私は若干困惑した表情を浮かべたものの、初対面の挨拶を無下にするわけにもいかず、なぁなぁな態度でそのまま肉じゃがの入った小さめの鍋を受け取り、引きつった笑顔で感謝を述べながら玄関の扉を閉めました。
これはまいった。
隣室に引っ越してきたばかりの見知らぬ女性から、得体のしれない善意を受け取ってしまった。
嫁さんが実家に戻って不在の今、あらぬ疑いをかけられてしまう可能性もなきにしもあらず。
ただ、こういった機会もそうそうないですし、他人の作った得体の知れない料理の味にも関心があります。
しかしながら最近ではメインのおかずに手が届かなくなってしまうほど食卓の副菜が増え続けていることもあり、如何にしてこの肉じゃがを処理するべきか……。
肉じゃがは未だ一口も食べずに冷蔵庫に入ったままです。
3日目となる明日にはそろそろ食べ切らなければなりません。
下手をすれば鍋の返却のタイミングで感想を求められる可能性も考えられないこともない。
ひとまずは適当にお腹が空いてきたタイミングで少しずつ肉じゃがを食べていきたいと思います。
※この話は実際に体験した出来事に基づいた一部フィクションです※
どの部分がどの範囲までフィクションであるのか、ノンフィクションであるのかは閲覧している方の想像にお任せします。














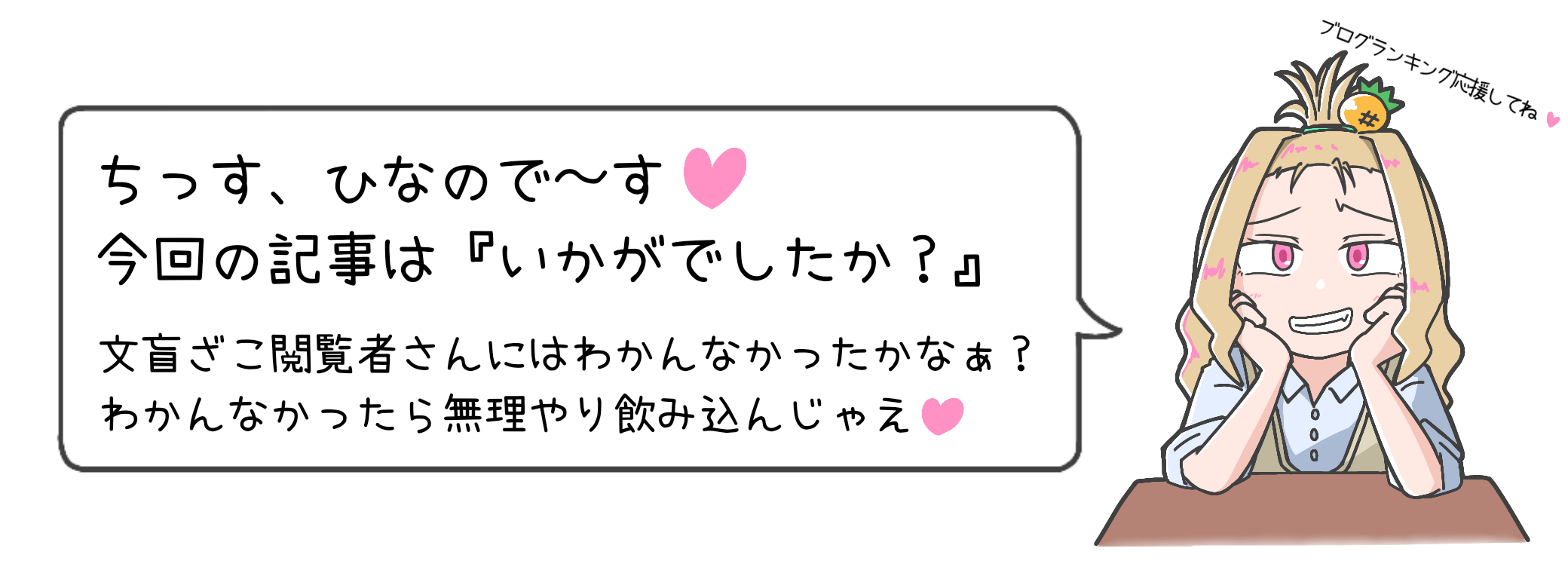




 【定次さん】
【定次さん】