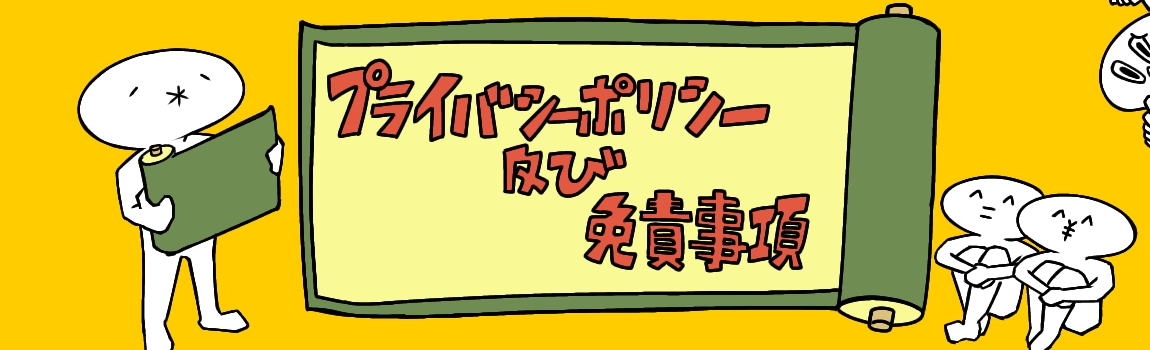【まとめ】AIタッグノベル!!『下衆と皮肉劇場〜ドッキリ殺人ヒーロー〜』
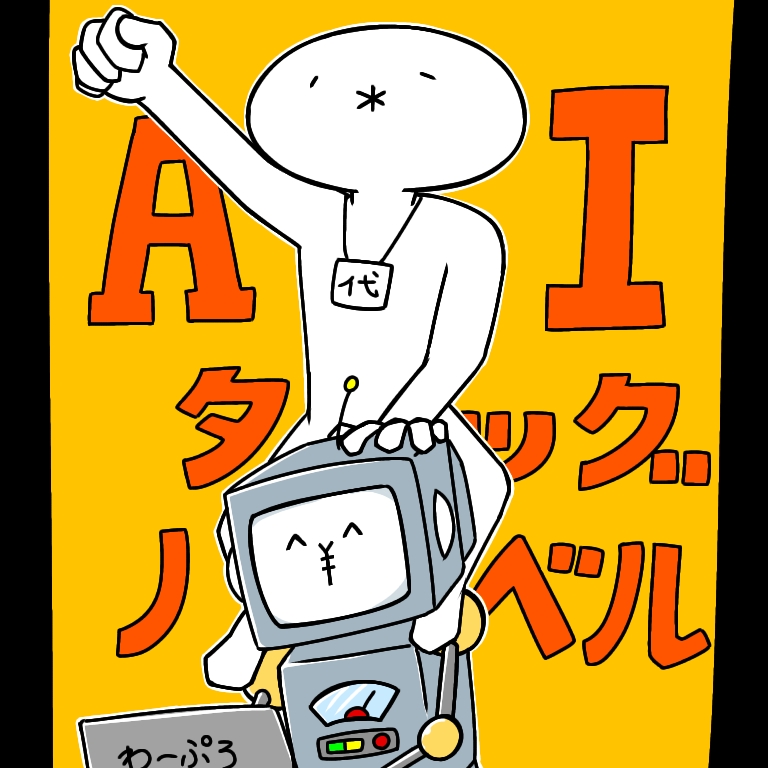
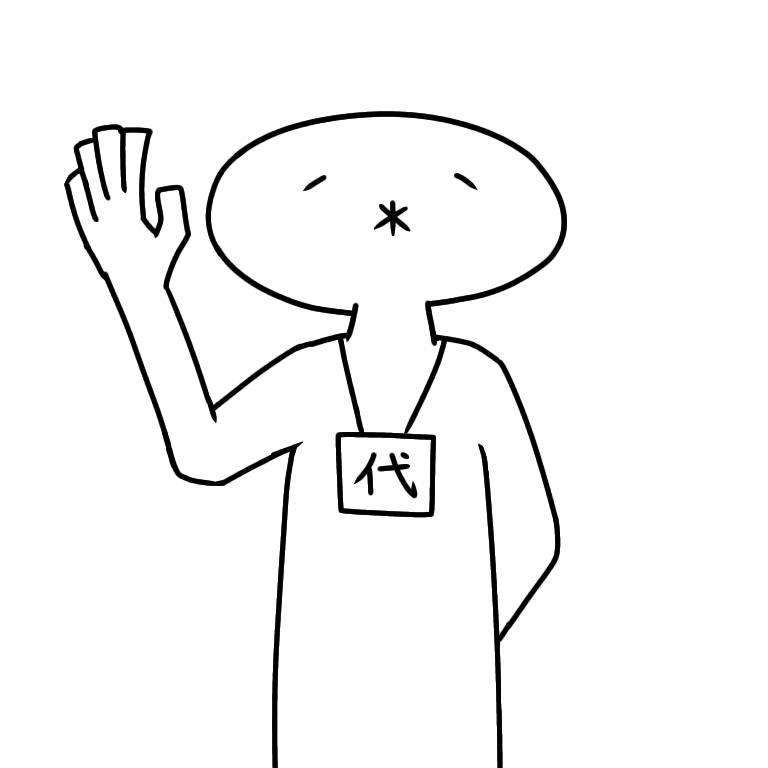
おはよう、皆の衆。定次さんです。
今回は先日まで更新していたAIタッグノベルのまとめとなります。
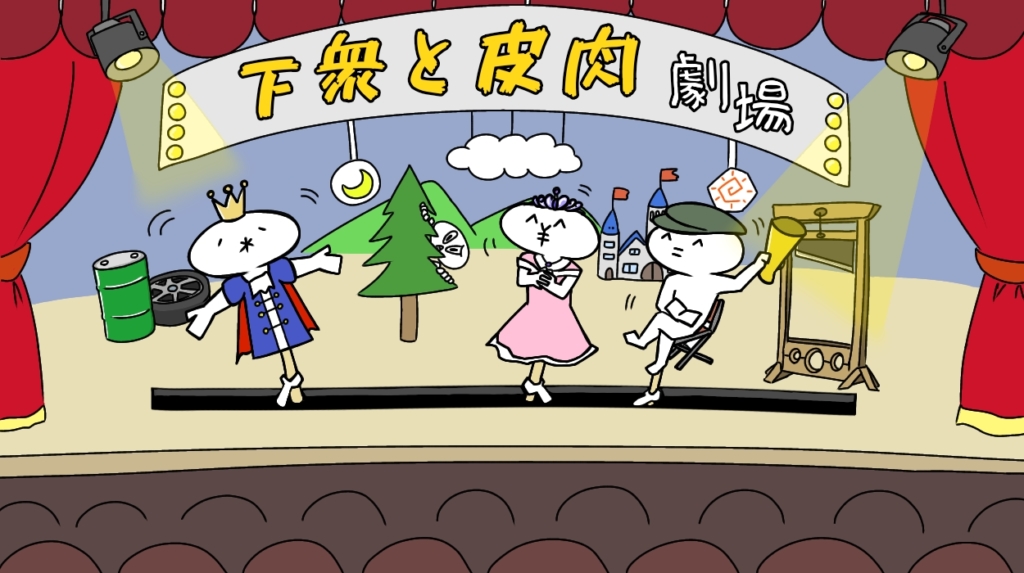
今日も今日とて平和であった。
このまま太陽の光を浴びたまま、呆けた面のまま飢えて骨になり、そのまま崩れてしまいたい……そう物思いに耽けながら縁側に腰掛ける男はどこか退屈そうであった。
太陽が地平線の向こうに沈まなくなってからはや1ヶ月と12日。この異常な現象を前に世界中の動植物は息つく暇もなくなり、次々と死に絶えた。
「夜のない世界がこんなにも退屈だとは思わなかった」
どういうわけかこんな異常な世界で生き延びている男はあまり太陽というものを知らずに今日まで生きてきた。
遮光性の高いカーテンで閉め切り、かび臭く変質してしまった実家の一室。外界を拒絶し、遮断された空間の中、これまたかび臭いぺちゃんこな布団を被って太陽光とは一切縁のない世界で生きてきた男がそこにはいた。
長い長い間、外の世界を見ようともせず、ただただ虚無な一日を何をすることもなく過ごしていた。
そんな男がいつしか外の世界へ踏み出す決心をした時、光が射す向こうには既に似たようで知らない世界が広がっていたのだ。
『夜がない』
ただそれだけのことが彼にとってはとても新鮮だったのだ。
しかしそれは彼が望んだ世界ではなかった。彼は今こうして暗闇の中にいるというわけではないが、その生活に慣れてしまっていたのだ。だから突然の光に目が眩みそうになる。そして同時に思ったのだろう。
あぁなんて退屈なんだろうと。
彼はふと思い立ったように立ち上がったかと思うと徐ろに部屋の隅へと向かい始めた。そこにある物は小さな本棚である。その中には所狭しに古びて変色した本の山が築かれていた。
いつの時代から集めた書籍だろうか。教養を深めるために買った哲学書、無惨にも踏み躙られた親の願いが籠もった自分への自己啓発本、ページ同士がカピカピに固まってしまったグラビア写真集なんかもある。あとは巻数がまばらな漫画がほとんどだが、どれもこれもホコリが被ってしまってまるで価値のないゴミのようにしか見えない。
「俺自身のちょっとした歴史だな」
いつまでも途切れることのない太陽光を背に浴びながら、逆光の中でフッと笑みがこぼれた。
……………………
しばらく埃を被った本の表紙に触れている内に何冊かをパラパラめくっていた手が止まる。
そこには色鉛筆で描かれたであろうカラフルでとても上手いとは言えない下手くそなイラストがあった。どうやらそれは絵本らしい。タイトルは"人魚姫"……内容はこうだった。
“昔々あるところに海に住む美しいお姉さんがいました。彼女はある日嵐に巻き込まれ、海に流されてしまった男の王子様を見つけました。王子様を助けた彼女でしたが自分が助かった時に代わりに命を落としてしまいます。
……………話はそこで終わっていた。
どうしてこんな絵本がこの本棚の中に入っているのか理解ができなかった。いくら雑に積み上げられた本の山とは言え、自らのヒストリーとほくそ笑んでしまえるほどの場所に置かれていたものとしてはあまりに異質……記憶にない代物なのだ。
当たり前の世界の当たり前の空間の中であり得ない物を手に取った男は、開ききった最後のページを前に少し考える素振りを見せた。
目の前を数匹の蝿が飛び回っている。
それを目だけで追うと、視線はそのまま自然と絵本の文字を追っていた。するとそこには先程とは違う文章が書かれていた。
そこに書かれている文章を声に出して読んでみる。
ー 私の命と引き替えに彼を助けることができた。それでいい。後悔などしていないわ。
だって私は彼を愛しているから 彼の笑顔が好き。私の名前を呼んでくれるあの優しい声で名前を呼ばれると胸の奥が暖かくなる。私が困っている時はいつも手を差し伸べてくれる。でも本当は辛いこともたくさんあってきっといっぱい我慢してきたはず。それでも自分のことを二の次にして誰かのために動けてしまう素敵なところが本当に大好きだった。
だからね。彼にお願いがあるんだ。もしあなたがまだこの物語を憶えていてくれたならその時は私の分もどうか生きて幸せになって欲しい。
これは私のワガママ。
ごめんなさい、こんな勝手で我の強い女のことなんて早く忘れちゃってください。
寒気がした。背筋が凍るとはまさにこのことを言うのだろう。
意味深な内容にも見えたが、男にとってはまるで身に覚えのない話だった。
忽ち狼狽えるやいなや、手に取っていた絵本を部屋の片隅へ放り投げると一目散に外へと駆け出した。
放置されて埃の掃き溜めと化していた部屋の隅へと雑に投げ捨てられた絵本はまた塵埃という闇の中へと埋もれ、やがて忘れ去られる存在へと戻ってしまった。
「はぁ・・・はぁ・・・」
恐怖から夢中で逃げ出した男は息を切らし、家から10mも離れたところでようやく我に返った。
そして辺りを見渡すとそこには見慣れぬ光景が広がっていた。
家を出た瞬間に目に入ってきた景色とは打って変わってそこは見知らぬ土地。見たこともない木々が鬱蒼と生い茂っており、薄暗く気味の悪い森であった。
ここは一体どこなんだ。
俺はこんなところに今まで住んでいたというのか?
しかしそう思ったのも束の間、再び視界に飛び込んできた風景に目を疑った。
今にも雨が降り出しそうなどんよりとした厚い雲。それに伴って広がる空模様に思わず溜息が漏れる。
しかしそれもつかの間のことで、その先に見えてきたのは再び異様な光景。
『喫茶店-竜の巣-』誕生である。
男が唖然とするのも無理はない。今現在自分が見ているものとは明らかに矛盾する風景が広がっているのだ。しかも先ほどまでの閑静な住宅街の風景ではなく、目の前には廃墟のような古びたビル群が立ち並んでいる。そんな奇妙な世界へといつの間にか転移してしまったようだった。
(何が起こっているんだ……)
状況が全く飲み込めず混乱している様子だったが、男は意を決して店に入ってみることにした。このままここで突っ立っているよりもまだ行動したほうがマシだと判断したのだろう。それにこんなところにいても仕方がない。
ドアノブに恐る恐る手を掛けるとギィっと錆び付いた音と共に数匹のネズミが飛び出してきた。
「うわっ!!」
いきなりのことに思わず体が仰け反った。
唐突な出来事に驚いてしまったのもあるが、何よりも何もいないと思っていたこの世界で久しぶりに生き物を見かけることができた事実が体を反射的に動かしたのだ。
仰け反った拍子で近くに置かれていた錆々の一斗缶に肘がぶつかる。中には何もなかったのか勢いよく吹き飛んだ後、大きくカランカランと高い音を立てて道路へと転がっていった。
「ギャアッ!!ギャアッ!!」
ビル群の間を木霊するようにけたたましい鳴き声が辺りに響き渡った。
どうやら今の騒音が奴らの注意を引いてしまったらしい。声のした方へ目を向けると、そこには3、4匹ほどの小鳥が飛び回っている姿が目に入った。
一瞬にして冷や汗が全身から溢れ出すような感覚に陥る。心臓の鼓動が徐々に早くなり呼吸の仕方がおかしくなっていく。明らかに異常な空気に飲まれていた。
まるで獲物を狙うようにジリジリとこちらに向かってくる鳥たち。逃げなければ、そう頭では思っているものの体は思うように動いてくれない。
気がつくと背中を向けて走り出していた。後ろからは羽音が聞こえてくる。
バタつくような羽音とともに鳴き声が一気に荒がる。
足元も覚束ないくらいに散らかった路地裏を踏みしめ、どこまでもどこまでも逃げる。古い油の臭いが鼻をかすめる中、かき分けるように足をもたげる。
――必死だった。普段体を動かしていなかったのを心底後悔した。すぐ後ろからはきっと鳥が目を光らせて嘴をこちらへと向けているだろう。
教養のない男にも弱肉強食の世界はよく理解ができた。他者に命を握られている状況がどれほどまでに窮屈であるか――掠れた吐息をぜいぜいと漏らしながら次第に深くなっていくどす黒いゴミ山の中へズブズブと体を埋めながらただただ前へと足を進め、やがて弱者は頭を大きく抱えてその場に立ちすくんだ。
―もうダメか……。
――――その時だった。
突然、何か大きな物が落下してくるような物凄い地鳴りが辺り一帯に轟いた。同時にバサバサと鳥たちが一斉に飛び立っていく。先ほどまでの喧騒が嘘のようにその場はシンとしていた。あまりの出来事に思考が停止する。だがそれもつかの間、男は目の前に現れた存在を見てハッとする。
巨大な生物。
先ほどまで男を追い回していたはずの小鳥たちを一呑みできてしまいそうなほどの巨大な怪物がそこにいた。そしてその生物と目が合った時、男の脳にはまるで走馬灯でも見せられたかのようにこれまでの人生の断片が流れ込んでいった。
(これが死か……)
気がつくと見慣れた天井が目の前に広がっていた。
慌てて体を起こし、周りを見回すとここが自室であることに気がついた。いつもと変わりのない汚らしくかび臭い実家の一室。
どうやら今しがたまで見ていた妙に生々しい光景は夢だったようだ。
安堵とともに深い溜め息を漏らす。
「やはり退屈な日常はそのままでいい。危険を冒してまで新鮮味を求めるなんて愚か者の考えることだ。」
ブツクサと小言を漏らしながら、何一つ変わることのなかった日常を鼻で笑って湿気を含んだ重たくぺしゃんこな布団へと大げさに潜り込んだ。
窓際にかけられた遮光性の高いカーテンが大きく開いている。
眩い光が射し込み、寝ぼけ眼に突き刺さる。男は顔をしかめながらその光の方向へ顔を向けた。そこには澄み渡る青空が広がっていた。どうやら朝から雲ひとつない快晴らしい。しかし男にとってはそんな天気など興味もないようですぐに視線を外すと再びまどろむように眠りについたのであった。
この男は怠惰な人間であった。
この世の全てが自分の敵であるかのように日々を過ごしていた。
親や学校といった世間の目が自分にとっての天敵に見えたのだ。しかしそれも無理はない。彼はこれまでずっとこの世界で虐げられ続けてきた。
「よっしゃ!キックベースしようぜ!」
小学生の頃。
放課後に遊びに誘ってくれるのは決まってクラスの中心人物の男子達だった。しかし彼らは皆運動神経抜群で勉強もよくできる所謂文武両道という類の子供だった。
対して俺はといえば授業中に教師の言うことをよく聞き、大人しく真面目でいることを信条に過ごしてきた子供だ。もちろん彼らと一緒にサッカーをするような活発な性格ではない。そもそも友達すらろくにいなかった。だから誘われたところで彼らの輪に入ることはできなかった。
そんなこんなで1人グラウンドの端っこに座って眺めているのが当時の俺の姿だった。
当然の如く、俺の周りにいる人はいなくなった。
特に辛いと思うことはなかった。寧ろ清々していた。
周りから味方と言えるような人間がいなくなったと言っても、敵が増えたわけでもない。
いじめられるきっかけは十二分にあったというのに誰も俺をいじめることはしなかった。
――クラスメイトたちは皆いい奴だった。
いつだって無関心を貫き、俺の存在を日常に溶け込ませてくれていた。
クラスのイベントがあってものけものにされた覚えもない。大した役回りがもらえることはなかったが、怠惰に毎日を過ごすには十分な立ち位置を俺に与えてくれていた。
つまり、平和だったのだ。
それはこの上なく居心地の良い場所でもあった。
だからこそ俺はこの場所に執着した。ここにいれば、少なくとも誰かに攻撃されることもなければ、嫌なことを思い出すこともない。そう思っていた。
そんなある日のこと。
いつもと同じように下校をしていると後ろから声をかけられた。
声の主は担任の先生だった。
何か話したいことがあるらしい。
一体なんだ? 全く思い当たる節はなかった。
少し不安になりながらもついて行った先には見知らぬ部屋があった。中に入るとそこは校長室のような造りになっており、ソファには白髪のおじいさんが腰掛けてこちらを見据えていた。その風貌はとても威厳のあるもので思わず姿勢を正してしまう。するとおじいさんは優しい声で話しかけてくれた。
「学校生活は楽しいかな?」
楽しいも何もこの日常は義務だ。義務に楽しいも何もあったものじゃない。
俺はわざとらしく顔をしかめ、首を傾げたまま天を仰いだ。
上を向いた視線に覆いかぶさるようにおじいさんは再び口を開いた。
「楽しいというわけでもないのかな?」
視線の片隅でおじいさんが少し悲しげな表情を浮かべたのが見えた。俺はすぐに目を背けるとたちまち口をへの字に曲げ、「で?」と生意気に返事をした。
急に視線が正面に向けられる。ガッと頭が掴まれたかと思えば担任の低く、そして重たい怒声を頭の上から浴びた。冷水を浴びたように全身から力が抜ける。
同時に心臓までもがギュッと縮み上がる感覚に襲われた。
担任は言った。
お前の生活態度は最悪だと。
怠惰で協調性もなくただのうのうと過ごすばかりで、その様子はこの学校の風紀を乱す行為であり決して看過することはできない、とも。その言葉をまるで死刑宣告のように感じながら俯いてじっと堪えていた。その言葉が終わるや否や担任はおじいさんに向かって一礼をしてから足早に部屋を出ていった。残された俺は再びゆっくりと頭を上げながら目の前に座ったままの人物へと恐る恐る目線を合わせた。
おじいさんは先程の雰囲気とは打って変わってにこやかな表情でこちらを見ている。
「今回何故呼ばれたかわかるかな?」
今度は純粋に顔をしかめる。先程とは逆の方向に首を傾げ、震える声で答えを返す。
「……叱るため、ですか?」
「違う。君は選ばれたんだよ。」
か細い声を遮るように、おじいさんは嬉々として立ち上がった。
意外と身長は高い。デスクの上に置いた手のひらが若干背伸びをしている。
興奮冷めやらぬおじいさんは段々と前のめりになりながら続けてこう言い放った。
「君なら世界を変えられるかもしれない。この腐ってしまった世界を救えるかもしれない。」
呆気に取られている俺をよそに彼は熱く語り始めた。
「この国はダメになってしまった。もうじき滅んでしまうだろう。だから私は救世主を探さなければならないと考えたんだ。そしてようやく見つけた。それが君だよ。」
そう言っておじいさんは右手を胸の前に出し手を広げて見せた。
掌にはいつの間にか銀色に光る小さな箱が置かれていた。大きさにしてタバコ1つ分程度の大きさだろうか。
それは見る限りなんの変哲もないただの箱だ。
「これはこの地域に纏わる呪物でね。本当は公然に出してはいけないんだ」
気がつくと手を伸ばそうとしていた。その瞬間、遮るようにおじいさんは血相を変えて俺の手を勢いよくはたき落とした。
「安易に手を伸ばすんじゃない!これが何なのかわかっているのか!」
さっきまでにこやかだった表情はまたたく間に鬼の形相へと変わり、おじいさんは掌に置かれた何の変哲もない箱を自身の背後へとさっと隠した。そしてブツブツと小言を唱えながらそそくさと部屋から出ていってしまった。
――結局、あの箱の正体は何だったのだろうか。
それから程なくして家に帰ることができたが、俺の中にはモヤがかかったような違和感だけが残っていた。あれだけ叱られたはずなのに全くといっていいほど心に響かなかったのだ。しかしそれとは裏腹に妙な使命感がふつふつと込み上げてきた。
――俺がこの国のヒーローになるのだ。
そう思った時には既に行動を起こしていた。
翌日、俺は学校へ行かず町を駆け回った。
まず向かった先は交番だ。そこにいた警察官は突然現れた中学生に対して少し驚いたようだったがすぐに優しい笑みを浮かべてくれた。
膝を折って目線を合わせて話を伺おうとする警察官を前に中学生は微笑み返すようにニコニコとしている。
後ろ手を組み、尚も視線を持ち上げて微笑む中学生に警察官は首を傾げる……その直後だった。
「あっ」
俺が声を上げた瞬間、既に警察官はその場にうずくまった。その首からはおびただしい量の血が流れ、先程まで優しい笑みを浮かべていた警察官は溺れるような声を漏らし、じきに倒れて動かなくなってしまった。
中学生は未だ温かいであろう鮮血が滴る刃物らしきものをだらりとぶらさげながら、その場に倒れた大人を見下ろす。その顔は変わらずにこにことしていて、何を考えているのか到底見当もつかない。
やがてゆっくりと動き出したと思えば、既に冷たくなってしまったであろう警察官にまたがり、その手に持つ刃物を強く握って大きく振りかぶった。そこで俺は逃げ出してしまった。
自分のやった罪悪感に耐えきれなくなって逃げ出さずにはいられなかった。走りながらも心の中では何度も謝罪を繰り返しながら俺は走った。息が上がる頃には俺は自宅近くの路地裏で力尽きるようにして倒れ込んでいた。そのまましばらく横になっていると誰かの話し声のような音が耳元で小さく聞こえてくる。聞き間違いではないようだ。音は徐々に大きくなるにつれて人の叫び声のような、何かの断末魔のような悲鳴のような、とても恐ろしいものが混ざってくるのがわかった。
嫌でも耳に入ってくる悲痛の叫びを聞きたくないと思い、両の手で必死に蓋をするがどうにも隙間を縫って漏れ出てくる。
「よっしゃ!キックベースしようぜ!」
そんな時、突如として耳を塞ぐ両手の間から陽気な声が入り込んできた。俺は思わず飛び起き、辺りを見渡すと目の前にはランドセルを背負った小学生がいた。
その子は楽しげに笑う少年に肩車されながら一緒に喜んでいる。2人はそのまま楽しげに走っていき、見えなくなったところで今度はボール遊びを始めた。それを遠目に眺めながら俺は大きくため息をついた。
(あぁ、そういえば今日は土曜日だったっけ)
今朝見た新聞の記事を思い出す。
昨夜、この町で高校生3人が行方不明になったそうだ。
3人とも仲の良い友人同士で深夜、いつもの溜まり場であった空き家に集合していたところを巡回中の警察が発見したらしい。警察はすぐさま110番通報したが犯人からの接触はなく、その後、捜索隊が派遣されて付近を隈なく探したところ血痕のようなものが見つかった。しかしそれだけで、それ以上の痕跡は一切なかった。
「この世界はどこかおかしい。まるで夢でも見ているようだ」
ヒーローになると志したのはついさっきだが、立て続けに起こるまやかしのような現実に俺は心を折らざるを得なかった。いや、折れるしかなかったのだ。
勢い良く駆け出した足は既に膝をつき、小学生ながらに俺は頭を抱えていた。
「俺はこの世界の何になればいいのだろう……?」
絶望の淵で天を仰ぐこの瞬間も、周りでは大小問わない無秩序な犯罪が蔓延っている。泥跳ねを食らったかのように顔に血を浴びて視界が真っ赤になる。つんざくような断末魔が聴覚を奪っていく。
俺が守るべき日常はもはやそこにはなかった。
ただ1つ、俺に残されたもの。
それが―――俺が手にする正義の刃。
それからの毎日、俺は寝る間すら惜しんで殺人を続けた。
あのおじいさんは言っていた。この呪物は選ばれた人間にしか扱えないと。だからあの時のおじいさんの言葉の意味をやっと理解することができた。確かに俺以外の人間が触れれば、恐らくあの呪物に触れることなく死んでしまうのだろう。
――そして、それはきっと俺も同じだ。
俺が手にしたあの銀箱が発していたのは、まさに死のオーラだった。
いつしかこの町も随分と寂れてしまった。寂れたというより廃れたと例えた方が的確だろう。
たった一人の子供が刃物を握っただけで水を打ったように静まり返った世界へと変わってしまったのだ。
死臭に覆われ、蝿やウジががたかるストリートを闊歩することに快楽を覚えてしまった。
建物の片隅からコソコソとこちらを伺う姿が垣間見られるが、視線を向ければたちまち影へと隠れてしまう。果たして俺はこの世界を救うヒーローとなれたのだろうか?一度折れた心へ寄せ木のように現れた呪物の刃物。傍から見れば悪そのものかもしれないが、俺は悪そのものであって今ここに必要とされている実感を受けて存在をしているのだ。
俺はこれからもこの凶器を手に持ち、悪を切り刻むことを誓い、俺自身を正義とすることに決めた。
ある日、路地裏を通りかかったところ偶然にも見覚えのある姿を見つけた。あの時に出会った、あの男の子だ。
彼は薄暗い道端で膝を抱えながら座っており、その瞳は虚ろに宙を見つめている。彼の周囲には大量の吐瀉物が散乱しており、そのどれもが原型を留めないほど酷く損傷しているものだ。鼻をつく臭いを嗅ぎながら彼のもとへ近寄ると、ふと彼と目が合った。
彼と俺は面識がないはずだ。しかし、目があったその瞬間にどこか通じるものがあった。
目を丸くし、ただ呆然とこちらを見続ける彼はしばらくして何かに気づいたように足早にその場を後にした。
特に理由はないが追いかけてみたかった。あの時、警官に刃物を突き立てながら何を思っていたのか……今ではどうだっていい。俺はただ片手に強く握りしめた刃物を露わにしながら、汚物にまみれた道を蹴散らしながら彼の通った足跡を一歩一歩踏みしめていった。
いつの間にか人気の失せた路地裏まで来ており、ここでようやく見失ったことに気がついた。
すると、突然後ろの方でガタンッという音が響いた。
振り返るとそこにいたのは、今まさに俺を追いかけてきたであろう少年の姿があった。肩を大きく上下させながら荒い呼吸を繰り返しているが、その表情はとても苦しそうだ。今にも倒れてしまいそうなほどの息切れを起こながら、必死の形相で少年は俺を見据えていた。
やがて少年は震える手で握っていたものを見せつけるように差し出すと、俺もまた同じように手を差し出してみた。
辺りに鮮血が飛び散った――と同時に冷たいような、熱いような痛みが手の平から上ってきた。
差し出した手の平を見てみると、浅く、そして細長い切り傷がついていた。
漏れ出すようにじわじわと溢れ出てくる血。薄暗い路地裏では真っ黒に見えたが、これは間違いなく俺の血だ。
呆気にとられていると少年の拳が飛んできた。危うく顎をかすめるところだったが、間一髪のところでかわし、前のめりによろめいた少年の腹部へと思い切り刃物を突き刺した。
これまでに感じたものと同じ鈍い感触が伝わってくる。
不安定な足場からつま先をもたげて倒れかかってくる少年を押し返すや否や、今一度深く刃物を突き刺した。
肉が裂ける感覚と共に生暖かい血液が刃先に絡みつく。それを目の当たりにしてもなお俺はこの刃を抜くことが出来なかった。
それは何故か? 答えは明白だった。
この子は、かつての俺なのだ――。
少年は今朝見た新聞記事で見た行方不明となっていた3人の内の一人だったのだ。そう考えると辻妻が合う部分が多くあることに気づく。
そうして俺は確信する。この世界の歪さを。
俺がこの世界で生きる意味を。
少年が俺の足にしがみついてきた。まだあどけないその顔には無邪気な笑みさえ浮かんできた。俺は無感情に刃物を振り下ろしては、この小さな命を絶ち続けた。俺が生きていくために。俺が存在するためには仕方のない事だと割り切って。
やがて、足元には血溜りが出来上がり、その真ん中で少年が仰向けに倒れている。
「ギャアッ!!ギャアッ!!」
その場を立ち去る俺の背後からけたたましい鳴き声が聞こえてくる。
激しい羽音とともに時折鳴き声が止むのは新鮮な血肉をついばむのに必死だからだろう。
かつての俺はこのまま鳥に食われていなくなる運命なのだ――この世界はこうして割り切って生きていくしかないのだ。
細い路地裏を抜けて明るい日が目の前に差し込んでくる――。
割れた窓ガラスに映る自身の体は血に染まり、とても醜い姿をしていた。咄嗟に開いた手が酷く痛む。
その手をまじまじと見つめながら、俺は思う。
俺はヒーローなどではなく殺人鬼だ。
ただの人殺しに過ぎないのだと。
俺はヒーローではない――。
そして殺人鬼として生きることを決めた俺はこれからもずっと戦い続けなくてはならないのだ。俺という殺人鬼を必要としてくれる人がきっとどこかにいるはずだから。
それが俺にとっての正義となる。
だから、
――俺はまだ死ねない。
~第1章:正義の終わり、正義の始まり~
完
―――西暦20××年7月某日早朝。
都内で連続猟奇的殺人事件が発生していた。
大量のパトカーが厳戒態勢で辺り一帯に停まっている。昇ったばかりの日差しで陰りとなったビルの隙間を赤色灯が何度も照らす。
――赤色灯が回る度に陰りから浮き出る顔。
全く眩しがる様子もなく、座った目と歪に持ち上がった口角。だらりと垂れ下がった両手には刃物が握られている。
慌ただしく走り回る警官は不思議とこちらを向くことがない。ゴミの掃き溜めのようになってしまった空間は既に現実世界と隔絶されているのだ。
俺はゆっくりと踵を返し、ゴミ溜まりの闇の中へと消えていった。
今日もまた、獲物を求めて俺は闇夜に紛れて街を闊歩する。
* その日の朝のニュースでは、また新たな行方不明者が出たということが取り上げられており、連日の報道内容に変化は見られないようだ。
ここ数日の間に東京都内で5人もの人間が姿を消しており、警察では事件との関連も視野に入れて捜査をしているらしい。
5人のうち4人は若い女性であり年齢もバラバラで接点も見つかっていないが、残る一人の被害者である15歳の男子高校生だけは行方がわからなくなって2週間が経過していた。
警察は身代金の要求などがないことから、何らかのトラブルに巻き込まれて殺害された可能性もあると見て、情報提供を呼びかけているということだ。
メディアも皆ミーハーなもので、日を追うごとに報道の規模も小さくなっていき、世間の関心も徐々に薄れていった。
何よりも法律がまともに機能していない昨今、人の1人2人がいなくなることは珍しいものではない。今回はたまたま近い範囲で消えた人数が若干多かっただけであり、ただそれだけだった。
人々は明日が我が身であるというのにいつだって他人事のようにニュースを傍観している。
小汚い部屋の傍ら、くしゃくしゃとシワだらけになった2日前の新聞を広げ、日に日に片隅へと追いやられていく今回の事件の記事を読んで俺は歯がゆさを覚えていた。
俺のために死んでいった尊い命の価値とはこんなものか。この記事が新聞からなくなってしまう頃には俺の存在も消えてしまうのではないかと焦燥に駆られ、いつからか右足は小刻みに震えていた。
そんなことをしても意味がないと分かっていながらも新聞紙を思い切り丸めて投げつけたくなる衝動を抑えながら、俺はテレビの電源を入れた。
いつも通りにニュースキャスターが映し出されると、彼は淡々と事件の続報を読み上げ始めた。
俺がまだこの世に存在できるかどうかを決める大事な一戦が始まる合図だ。
昨日の時点で既に3人の人間の殺害に成功している。俺はまだ生きているのだ。あとは今日新たに誰かを殺すことができれば、この世で生きていける。それが分かった瞬間に、俺は全身に熱を帯びるような興奮を覚えるのだ。それはまるで血液が沸騰しそうになるほど激しいものでもある。
「でも全部フィクションだよね」
背後から声がしたと思った次の刹那、テレビは真っ二つに割られた。俺の手には刃渡り20センチ程のサバイバルナイフがある。それを振り下ろしたのであろう人物の足元には液晶画面が砕け散っており、その破片が散らばっていた。
俺には分かる。こいつは敵だと。
しかし何故?一体どこから入ってきた?そもそもどうやってここに入り込んだ? 様々な疑問が次々と浮かんでくるが、俺は構わずに振り返って勢いよく突進する。
相手の姿はまだはっきりと見えないものの体格は小柄で華奢な男だということが分かるくらいの距離まで接近すると、男は手に持った何かを構えて光を放つ――フラッシュライトのようなものだ。一瞬怯んでしまいそうになりつつも俺は相手の手を掴み捻り上げた。そして、すかさずその顔面を拳が軋む程に力を込めて殴りつける。
心地良い感触が伝わってくる。鼻の軟骨が潰れる感触――クリーンヒットだ。
相手の顔をはっきり見る前から顔を潰してしまうのも申し訳ないとほくそ笑む俺はつくづく性格が悪い。
足元に転がったフラッシュライトを拾い上げ、既に伸びてしまった男を照らす。
到底見れた顔ではないだろうとは思いつつも、急に襲ってきたこいつが一体何者なのか……ピンと向けられた足から徐々にライトを持ち上げていき、その面を拝む。
顔の中心からドクドクと溢れる鮮血に汚らしさから覚える若干の嫌悪と、その優越からくる些細な興奮が呼吸を荒くさせる。
まじまじと見つめ、次第に気持ちが落ち着いてきたところでとあることに気が付いた。
「この顔、どこかで……?」
どこかで見たことがある。しかもごく最近だ。思い出せない――記憶の断片を探るように、俺はライトで照らし続ける。
ライトを当てたところで顔が見えるはずもないのだが、ふと脳裏をよぎったのは、俺の顔だった。鏡の中の自分の姿と目の前の男の顔とが似ている気がしてならなかったのだ。だがそんなこと有り得る筈がないと即座に頭の中で否定し、俺は男の服を脱がせて身元を確認しようとするが……そこでようやく俺は確信に至る。男が着ている服は俺が通っている学校の制服ではないか、ということだ。
すぐにその場から逃げ出したかった。
だが、『もしかして』という好奇心が体を掴んで離さない。しばらくの間硬直し、誰に見せるわけでもなく考える素振りをしてみせた。落ち着きを取り戻したかったのだ。
強く打つ脈動とギトギトとしつこく張り付く汗が生を実感させる。時折飲み込む唾の音も聞こえるくらいに静まった一室の中、「ぎゃあっ」という外から聞こえた鳴き声を耳にして俺は遂にその場にへたり込むように腰を落とした。
恐怖心や緊張感などとうに超えてしまっていた。もう何も考えたくない。
恐る恐る扉を開けると、そこには頭部のない女性の死体と、返り血を浴びて佇む先程の男が居た。俺は思わず叫び声を上げそうになるが、男は何も言わずに黙っているだけだ。俺がやったのか、と問い掛けると、無言のままゆっくりと首を縦に振る。その動作を見て、また、死体の首元を見るなり俺は全てを悟った。
首が綺麗に切れていることに加えて、恐らくあの鋭利な刃物によるものだろう、傷口の周りからは皮膚だけでなく肉がえぐれていたのだ。まるで何かを食い千切った後のように……。俺には分かったのだ、こいつは俺を殺しにやって来たんだと。それも、ただ殺しにくるだけじゃなく、俺のように生き返らせることが目的なのだ。
――プツンという音が聞こえた。
いや、聞こえたのは気のせいかもしれないが、ここで俺はようやく我に返った。
プツンという音は緊張の糸が切れた音だったのだろう。何もかもがどうでもよくなった。
窓の隙間から入り込んでくる日差しによって次第に明るくなっていく一室。血みどろに塗られたその見慣れた一室はとても居心地が悪く感じた。
「もうどうでもいいや」
手に持った刃物を首に当てて静かに目を閉じる。いつの間にか呼吸も穏やかになり、心拍も怖いくらいに落ち着いている。
大きく息を吸い込んだところで歯を食いしばる。そして思い切り柄を握った手に力を込めた。
首の皮膚に弾かれて大きく折れ曲がってしまったナイフ。殺したと思いこんでいた人たちはいつの間にか皆立ち上がっていてニヤニヤと口角を持ち上げながらこちらを見下ろしている。
「テッテテー!!ドッキリでしたー!!」
皆が俺を一斉に殴り始めた。
俺は死んだふりをするしかできないが、その痛みすら嬉しく思えた。
そう、これは全部フィクションなんだ。夢の世界なんだから何が起こってもおかしくない。きっと俺は悪夢でも見ているのだろうと、殴られながらもぼんやりと考えていた。
頬に冷たい何かを感じた俺は目を覚ました。昨晩のことを思い出す。俺は確か――そう、テレビを見ながらソファの上で横になっていたはずだ。だが今は自室のベッドの上に居るということは、誰かが運んでくれたということだろうか。それとも――
俺は大きく深呼吸をし、冷静さを取り戻そうとする。そして、枕元の時計を手に取って時刻を確認する。
11時26分……
平日だと言うのに随分寝てしまったらしい。
今日は休日だと安堵する反面、俺は昨日のことが現実だと確信するに至る理由を2つほど見つけた。
1つ目は部屋の片隅に置かれた大きなキャリーケース。恐らく旅行用に購入したものだと思う。
2つ目は姿見に映った自身の姿だった。ブクブクに膨れ上がった顔は打撲で青黒く変色しており、肌着はまるで追い剥ぎにでもあったかのようにボロボロだった。ところどころに飛び散った血飛沫は恐らく俺自身のものだろう。
体がうまく動かない。重いのと同時に痛い。関節がギシギシと軋んで針金に縛られているような錯覚に陥っている。
頭が重く、瞼も腫れ上がっているので薄暗い周りがよく見えないが、気配は感じる。
後ろに何人もこちらを見下ろして立っているのが感じられる。
俺の視界がはっきりとしていないからなのかよく分からないが、皆一様に口を閉ざしているようだった。
そんな中、聞き覚えのある男の声が耳に入った。
俺を殺した犯人の声だ。
声の方に顔を向けようとすると眼球に違和感を覚えた。何か液体のような……血?のようなものが垂れてきて思わず拭うとべっとりと赤い血液が指に付着した。それを舐め取るように口に入れる。鉄の味だ。どこか懐かしさを覚えるこの味わいは俺の記憶を呼び起こす――あぁ、これは間違いなく俺の血だ。
俺は死んでしまったんだ。そう理解してしまえば、途端に体の力が抜けていく。
もうどうなってもいいと全てを他人任せにして目を瞑る……。するとまた眠気が襲ってきてそのまま意識が遠のいた……。…………
次に目が覚めた時にはすっかり夜になってしまっていた。
周りを見渡すと何も変わりない世界が目に入った。
姿見に映った自身の顔貌も全て見覚えのあるいつもと変わらないものだ。照明を点けると部屋は明るく照らされ、どこを見ても到底荒れているわけでもないし、気配を感じるわけでもない。
テレビからはしょうもないバラエティが流れ、作ったような笑い声が静かな一室に響き渡る。
――あぁ、俺は救われたんだ。
心から安堵した。これまで見てきたものが一体何だったのか決して理解できるものではなかったが、安心したのと同時に大きく疲れがやってきた。
これまでずっと眠っていたというのに、ゆっくりと休んだはずだというのに再び眠気に襲われた――。
…….
――ガチャッ!!!! 扉が激しく開けられる音に俺は飛び起きるようにして体を起こした。
心臓の鼓動がうるさい。汗も尋常じゃない程吹き出ている。呼吸は浅く、全身は震えて思うように動くことが出来ない……。
だが、すぐに落ち着きを取り戻すことができた。玄関にはスーツを着た一人の女性が立っているだけだ。
その女性の目は赤く充血していて頬には涙を流した痕跡があった。女性は靴を脱いで部屋に上がるなり俺の姿を見て泣き崩れるように抱きついたのだ。
女性に優しく抱きしめられながら頭を撫でられている間、次第に記憶を取り戻して来る。
これはドッキリだったんだと……。
終わり。
―――――
どうだったでしょうか。皆さんも夢を見たことがありますよね。私自身、最近まであまり夢を見ることがなかったのですが、久しぶりに見た夢の内容があまりにも怖かったので短編として書き起こしました。
夢というものは本当に不思議ですよね。現実では起こり得ない事が次々と現れて、夢の中ではそれが普通なのだと認識させられるんですから。
今回題材にした夢は正真正銘、悪夢です。皆さんはどんな内容だったと思いますか?ぜひ感想をお聞かせください! それではお楽しみに!! 皆さん、こんにちは!! 本日も最後まで読んで頂きありがとうございます!! 今回はホラー系で書いてみましたが、いかがでしたか?少しでも恐怖を感じて貰えていればいいなと思っています!!(*’∀’)ノシ
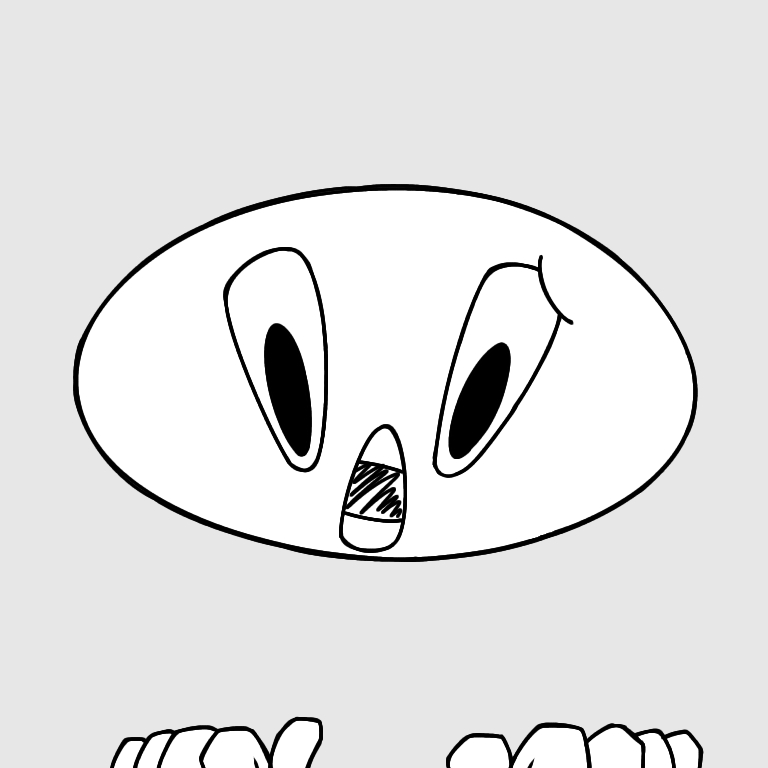
総合評価:★☆☆☆☆
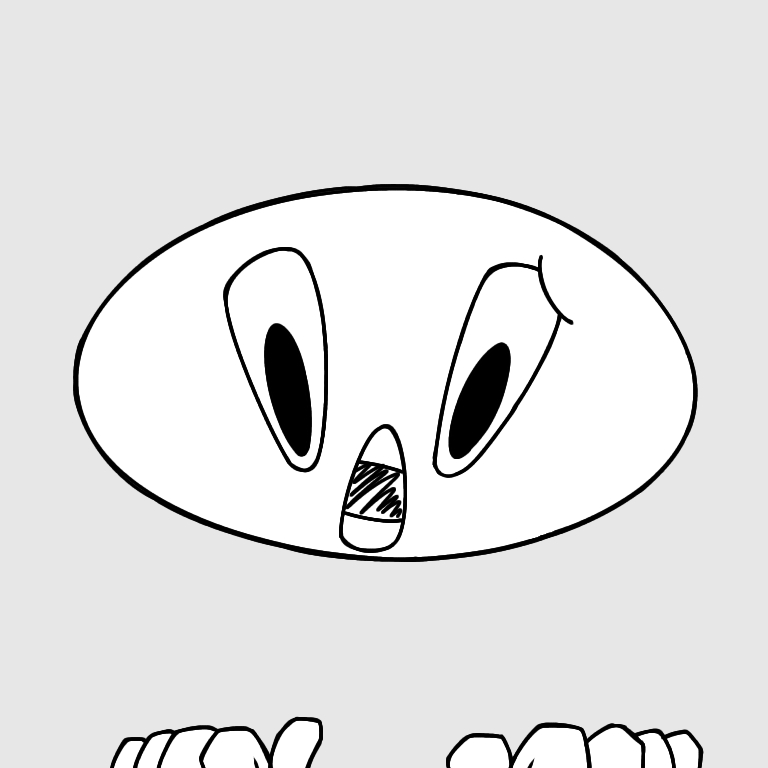
クソです。









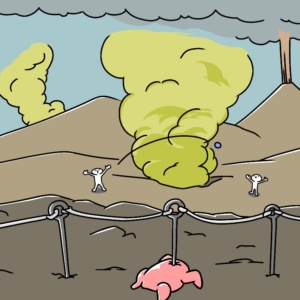




 【定次さん】
【定次さん】